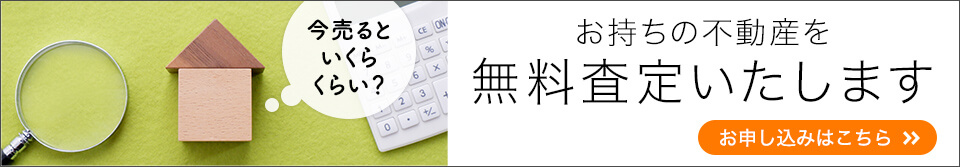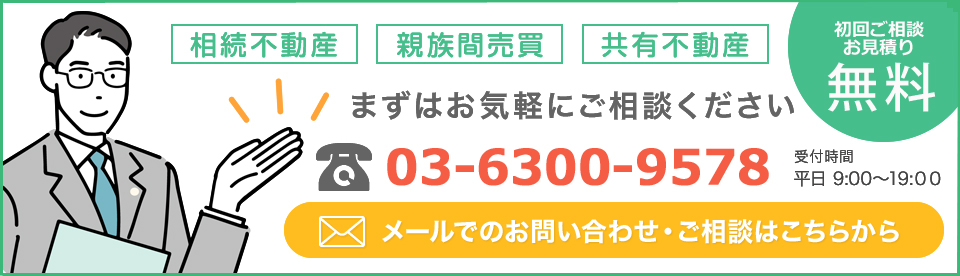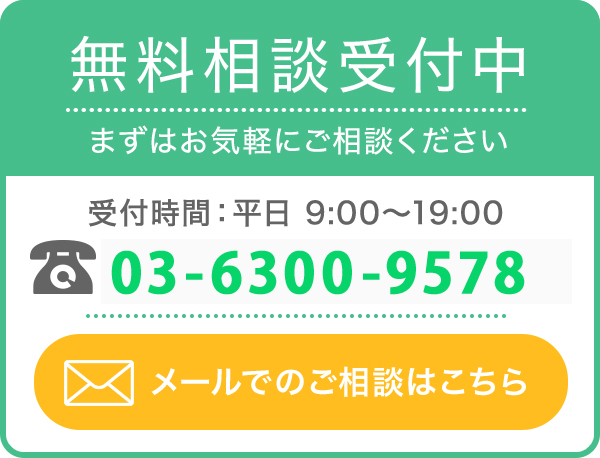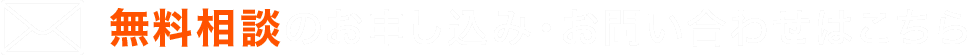親が老人ホームや介護施設に入居したあと、空き家となった実家をどうすべきか悩んでいる方へ。
「親の家を売却したいが、認知症で判断能力が不安」「空き家のまま放置すると税金や管理費がかかる」「相続の前に家族信託や成年後見制度を使っておきたい」—そんな声が増えています。
親の家に住むという選択もありますが、すでに持ち家がある場合や、親の家が今の生活圏から離れている場合などは、なかなかそのようなわけにもいかず、現実的には売却や管理の選択が必要になります。
ここでは、親の家の売却に関する法的な選択肢(任意代理・成年後見・家族信託)、空き家に関する税制優遇(3,000万円控除など)、認知症発症時の対応、相続との関係などを司法書士の視点からわかりやすく解説します。
目次
- 老人ホームに入る親の家を売却するメリット・デメリットとは
- 親の代わりに家を売るには? 認知症や施設入居時の対応方法
- 売却のタイミングはいつがよいか?
- 中野リーガルホームならではの幅広いサービスで介護施設入居をサポート
老人ホームに入居する親の家を売却するメリット・デメリットとは
親が老人ホームや介護施設に入居したあと、空き家となった実家をどうするか悩む方は少なくありません。家の所有者が親本人である以上、売却には親の意思確認が不可欠です。とくに認知症などで判断能力が低下している場合は、成年後見制度や家族信託などの法的手段が必要になることもあります。
親にとっては、長年住み慣れたマイホームを手放すことへの抵抗感が強く、「売りたくない」という気持ちも当然のことです。
しかし、空き家を放置したままにすると、固定資産税や維持費がかさむだけでなく、近隣トラブルや資産価値の低下につながるリスクもあります。

まずは、親の家を売却することで得られるメリットと、注意すべきデメリットを整理したうえで、家族で冷静に話し合うことが大切です。相続や資産管理の観点からも、早めの検討が後悔のない選択につながります。
メリット1:売却したお金を入居費用に充てられる
老人ホームや介護施設の入居費用は、施設の種類やサービス内容、介護度によって大きく異なります。
初期費用や月額費用に加えて、将来的に介護度が上がることで、必要な支出が増える可能性もあります。現在は年金や介護保険でまかなえていたとしても、長期入居となれば資金が不足するリスクも考えられます。
そのため、持ち家を売却して入居費用に充てるという選択は、老後の生活を安定させる有効な手段となります。「この先、何年施設で暮らすことになるのか分からない」という不安があるからこそ、資金に余裕を持っておくことは、精神的にも大きな安心につながります。
メリット2:管理費用や固定資産税がかからない
親の家を売却せずに維持する場合、建物や庭のメンテナンスが必要になります。
定期的な清掃や点検、修繕を行わなければならず、遠方に住んでいる場合は通うだけでも交通費がかさみます。マンションであれば毎月の管理費、修繕積立金の支払いも続ける必要があります。

さらに、固定資産税・都市計画税などの税金も毎年かかります。空き家のまま放置していると、資産価値が下がるだけでなく、近隣トラブルや防犯面の不安も生じやすくなります。
よほど財産に余裕がある場合を除けば、これらの維持費を介護費用にまわした方が、親子ともに安心して生活できるのではないでしょうか。
自宅を売却することで、空き家の管理負担や税金の支払いから解放され、介護施設での生活資金に充てることができます。
メリット3:売却時に税金の優遇が受けられる
不動産を売却して利益が出た場合、つまり購入時より高く売れた場合には、譲渡所得税が課税されます。しかし、居住していた家を売却する場合には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例※」という税制優遇を受けることができます。この特例が適用されれば、課税対象となる譲渡所得を大幅に減らすことができ、結果として大きな節税につながります。
ただし、この特例を受けるためには、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却する必要があります。ですので売却した場合の譲渡所得税がかかることが見込まれる場合には、早い段階での売却を検討すべきでしょう。
※「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用を受けるためには期限以外にも要件がありますので、ご注意ください。
デメリット1:老人ホームを退去した場合、住む場所に困る
老人ホームに入居したあとでも、必ずしもその施設が終の棲家になるとは限りません。
本人が施設の生活になじめず退去を希望するケースや、他の入居者とのトラブルなどによって施設側から退去を勧告されるケースもあります。
そのような場合、帰る場所があるだけでも一時的な安心につながります。そういった意味では、親の家をすぐに売却せず残しておく選択にも一定の価値があります。
ただし、退去後にその家で一人暮らしを続けられるかどうかは、介護の必要度や生活環境によって大きく異なります。結果的には、親族による引き取り介護や、別の施設への再入居を検討する必要が出てくることもあります。
施設入居後の生活が長期に安定するとは限らないからこそ、売却のタイミングや代替住居の選択肢についても、事前に家族で話し合っておくことが大切です。
親の代わりに家を売るには? 認知症や施設入居時の対応方法
原則として、不動産の売買契約は所有者本人が契約内容を理解し、意思表示をしたうえで締結する必要があります。そのため、親の家を売却するには、親自身が売却に同意し、契約に立ち会うことが基本となります。
しかし、親がすでに老人ホームや介護施設に入居している場合、売却に関する手続きや不動産会社とのやり取りを本人が行うのは大きな負担になります。高齢による体力の低下や移動の困難さを考えると、現実的には家族が代わって動く必要が出てくる場面も多いでしょう。
さらに、認知症などで意思能力が低下している場合には、たとえ契約書に署名・押印があっても、その契約自体が無効と判断される可能性があります。
このような場合には、「成年後見制度」や「家族信託」などの法的手段を活用することで、親の代わりに家を売却することが可能になります。
ここでは、親の判断能力の有無や施設入居の状況に応じて、どのような方法で売却手続きを進めるべきかをケース別にわかりやすくご紹介します。
1.「任意代理人」を立てて親の家を売却する方法
親が不動産の売却に同意しており、認知症などによって「意思能力に欠ける」状態ではない場合、「任意代理人」を立てて家の売却をすることができます。任意代理人には誰でもなることができますので、子が親の代わりに売却活動を行うことも可能です。
代理人として不動産を売却するには、親(所有者)本人からの「委任状」が必要となります。委任状に特に決まった書式はありませんが、多くの場合は不動産会社側で用意してくれたりフォーマットを用意してくれるため、事前に相談してみると安心です。

委任状には、どのような権限を代理人に委任するのかを明確に記載する必要があります。
親子間で権限の認識にズレがあると、後々トラブルになる可能性もあるため、売却条件や希望についてはしっかり話し合い、委任状に反映させておきましょう。
また、委任状は公証役場で公正証書として作成することをおすすめします。法的な裏付けがあることで、売却手続きがよりスムーズかつ安全に進められます。
なお、任意代理人はあくまでも親の意思を代行する立場です。売却活動を進める際には、可能な限り親の希望を尊重し、丁寧な対応を心がけましょう。
※「任意代理人」の制度を利用したとしても、売却の手続きをすべてを任意代理人のみで代わりにすることはできません。
例えば売買の登記の手続きを司法書士がするには任意代理人がいたとしても、原則所有者である親御様の本人確認・意思確認が必要で、署名押印も親御様自身にしてもらう必要があります。
しかし、「意思能力が欠ける」状態であると判断される場合、任意代理人による売却は認められません。その場合はどうすればよいか、次項でご説明いたします。
2.親が認知症の場合は「成年後見制度」を利用して売却
親が認知症などにより「意思能力を欠く状態」と判断された場合、不動産の売買契約などの法律行為を本人が行うことはできなくなります。ですがそのような場合でも「成年後見制度」を利用することで、親の代わりに家を売却することが可能になります。
「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な方の財産や権利を守るために設けられた法的な仕組みです。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類がありますが、すでに認知症の症状が進行している場合には、「法定後見制度」を利用することになります。
家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、審判が確定すると、家庭裁判所の判断により「成年後見人」が選任されます。
「成年後見人」に選ばれた人は、本人に代わって不動産の売買契約を結ぶことができるようになります。ただし、居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となります。
成年後見制度は、親の財産を守るうえで非常に有効な制度ですが、利用にあたってはさまざまな制約や注意点があります。
「成年後見人」を立てる場合の注意点
途中で制度の解除はできない
成年後見制度は、一度家庭裁判所の審判が確定すると、原則として途中で解除することはできません。売却が終了した後も継続されますので、本人の財産は家庭裁判所の監督下のもと成年後見人が管理し続けることになります。制度の終了は、本人が亡くなるか、意思能力が回復したと裁判所が判断するまでとなります。
また、成年後見制度は本人の財産を保護することを目的としているため、資産運用や生前贈与などの自由な財産活用は認められません。成年後見人は、家庭裁判所に対して定期的に財産管理の報告書を提出する義務があり、厳格な監督のもとで活動することになります。
親族が成年後見人に選ばれるとは限らない
成年後見人の選任は家庭裁判所が行いますが、必ずしも親族が選ばれるとは限りません。親族間での意見の対立や、財産の使い込みが懸念される場合には、弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人として選任されるケースも多く見られます。
親族以外の専門職が成年後見人となった場合には、報酬の支払いが必要になります。報酬額は月額2万円〜6万円程度で、本人の財産から支払われることになります。
申立てから売却までには時間と手間がかかる
成年後見制度を利用するには家庭裁判所に申立を行う必要があります。
申立書類を提出すると審理が始まり、書類の審査や面接、場合によっては意思による鑑定も行われます。審理が終わると裁判所により後見開始の審判、成年後見人の選任が行われます。申立てから審判までにかかる期間は1~3カ月程です。
成年後見人が決まり、ここからようやく売却活動を開始することができますが、居住用不動産を売却する際には成年後見人が裁判所に申立てを行い許可を得る必要があります。
売却が本人の利益になると裁判所が判断した場合にのみ許可が下りるため、例えば「売却しなくても施設入居が可能」と判断された場合には、許可が下りない可能性もあります。
3.「家族信託」を利用する
認知症対策のため、元気なうちに「家族信託」のスキームを提案します。
親が元気なうちに「家族信託」の仕組みを整えておくことで、将来的に認知症などで判断能力が低下した場合でも、子どもが不動産の売却手続きを進めることが可能になります。
法律上、不動産を売却する権限は所有者本人にしか認められておらず、たとえ子どもであっても親名義の家を勝手に売却することはできません。
しかし、「家族信託」という制度を活用すれば、親が子に「不動産を売却する権限」を渡すことができます。これは、親が子を信じて託すという意味での“信託”であり、親が手続きできない状態になっても、託された子どもが不動産の売却を進めることができる仕組みです。
このように、家族信託は「認知症対策」としても有効であり、将来の不動産管理や売却をスムーズに行うための手段として注目されています。
家族信託を組成するには、法的な観点だけでなく、税務面の検討も欠かせません。
また、不動産を信託財産として扱う場合には登記手続きが必要となるため、司法書士のサポートが不可欠です。制度の仕組みや手続きの流れについては、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
売却のタイミングはいつが良いか?
税金の優遇制度を受けるためには
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」という税制優遇を受けることができます。
この特例を適用するには、「住まなくなってから3年目の12月31日までに売却する」ことが条件となります。
売却によって譲渡所得税が発生する見込みがある場合は、この期限が一つの判断基準となりますので、早めの検討が重要です。
認知症を発症すると売却手続きが複雑に
親が認知症を発症し、「意思能力が欠けている」と判断された場合、通常の売却手続きはできなくなります。
その場合は、成年後見制度を利用して家庭裁判所に申立てを行い、後見人の選任や売却許可の取得が必要になります。
これには時間と手間がかかるため、認知症の兆候が見られる場合は、売却を先延ばしにしない方が安心です。
老人ホームから退去する可能性も考慮
では、老人ホームに入居した直後に家を売却すればよいかというと、慎重な判断が求められます。施設の生活は実際に入居してみないとわからない部分も多く、特に入居初期は環境の変化になじめず、不安を感じる方もいらっしゃいます。
そのようなときに「もう帰る家がない」と感じると、精神的な負担が大きくなる可能性もあります。
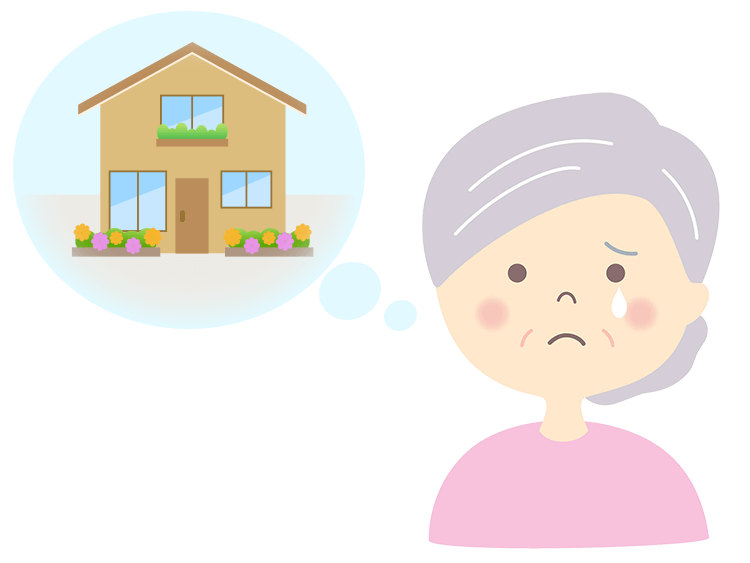
また、「思っていたような介護が受けられなかった」「他の入居者と合わなかった」などの理由で、やむなく退去するケースもあります。
その場合、新しい施設が見つかるまでの間に一時的に戻れる家があると、親も家族も安心できます。
売却のタイミングは、税制優遇の期限や認知症リスクだけでなく、施設での生活が安定しているかどうかも含めて、総合的に判断することが大切です。
このように売却のタイミングはそれぞれの事情により違ってきます。上記の他にやはり金銭的な余裕があるかどうかも関わってきますので、しっかりと検討して決めることが必要です。
中野リーガルホームならではの幅広いサービスで介護施設入居をサポート
中野リーガルホームでは、司法書士としての専門知識を活かしながら、「不動産売却」「成年後見制度」「家族信託」「身元保証」「老人ホームの無料紹介」など、介護施設入居に伴う幅広い課題に対応しております。
親の家を売却したい方、認知症対策を検討されている方、施設入居後の生活設計に不安を感じている方へ、安心してご相談いただける体制を整えています。
不動産売却の仲介と法的サポート
当事務所では、宅地建物取引士の資格を持つ司法書士が不動産売買の仲介をしております。
単なる売却手続きにとどまらず、相続や認知症リスクを見据えた法的アドバイスも含めて、安心・安全な取引をサポートいたします。
- 委任状の作成や任意代理人としての売却代行も対応可能
- 成年後見制度や家族信託との連携もご提案
- 相続登記や資産整理まで一括サポート
親御様の不動産売却に関して、後々のトラブルを防ぐための法的配慮を徹底しております。誠実な対応をお約束いたしますので、どうぞ安心してご依頼ください。
老人ホームの無料紹介サービス
介護施設を探している方には、老人ホーム選びの無料サポートを行っております。介護業界に長年携わってきた社会福祉士が、身体状況やご希望に合わせて最適な施設をご紹介いたします。
- 初期費用や月額費用の試算
- 資産+年金で生活が成り立つかの確認
- 空き家となる自宅の売却・活用提案
- 相続対策・残置物処理・身元保証・財産管理なども一括相談可能
施設見学や体験入居の手配も無料で承っております。
成年後見制度の申立てと手続き、継続支援
認知症などで意思能力が低下した場合に備え、成年後見制度の申立て書類作成を司法書士が代行いたします。申立て後も、ご家族が後見人に選任された場合の継続的なサポートを行っております。
- 家庭裁判所への申立て書類の作成・収集
- 後見人選任後の報告書作成や財産管理支援
生前対策・認知症対策のご相談
「今は元気だけれど、将来が不安」という方には、家族信託や任意後見制度の活用をご提案しています。相続トラブルを防ぐための遺言書作成や、認知症発症後に困らない財産管理の仕組みづくりをサポートいたします。
- 家族信託による不動産売却権限の事前委任
- 任意後見契約による将来の備え
- 相続・資産整理・老後の生活設計まで一括対応
中野リーガルホームでは、不動産売却だけでなく、介護・相続・認知症対策までをトータルで支援いたします。ご相談・お見積りは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。